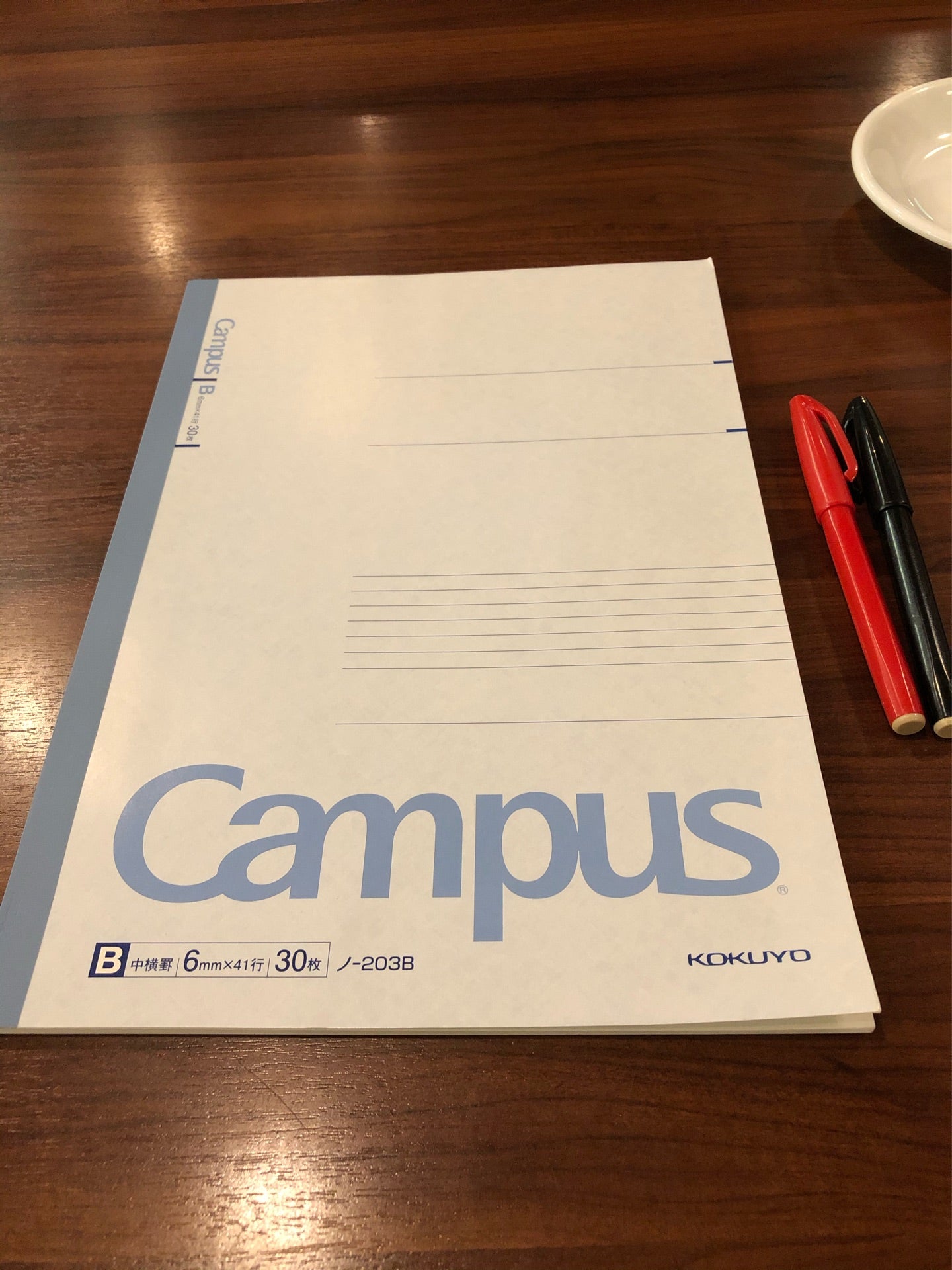藤田晋bot藤田晋bot 現在発売中の日経アソシエの私の連載で、
「耐える力」について書きました。
「答えは必ずある」と決めてかかる思考は
困難な仕事をする上でとても大事なことです。
誰が見ても正しいと思えるような仕事は、
実は凡庸になりやすく、競争も激しいです。
誰が見ても逆境に見える仕事は、
やり抜くことができれば、唯一無二に
なれる可能性があります。
しかし、その過程では、不安に打ち克ち、
批判に耐え忍ぶ強い精神力が必要です。
先日、堀江さんとビジネスの話をしていた時、既に市場で勝敗が決まってしまったように見えるサービスについて、
堀江さんが
「まだ絶対行けると思うんだよね」
と言い切っていました。
それに対して、私は
「もう絶対無理だと思うよ」
と反論していたのですが、その後、
そのことを少し反省しました。
ネット業界の歴史を振り返ると、
「絶対行けると思う」と思いこんだ人
の存在が市場を切り拓いてきた
からです。
アリナシが誰もよく分からないものを、
気合でアリにもっていったと言い換えてもいいかも知れません。
堀江さんが前からあるそのサービスを
初めて触ったのが仮出所して1か月少々
という点だけ若干気になりましたが、
堀江さんのような精神的に強い人は、
またネット業界で何かを起こす可能性が
あると思います。
叩かれても気にしない精神タフネスを
持ち合わせているからです。
私も結構打たれ強いほうですが、
ネット業界で何かを起こしたい人は、
「答えは必ずある」
と決めてかかることと、
「耐える力」
を鍛えることがお勧めです。
田中悠太のトーク
トーク情報田中悠太 田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot 実は昨年末から「憂鬱でなければ仕事じゃない」
の続編の製作に取り掛かっています。
往復書簡ではないのですが、見城社長の
原稿が先にどんどんあがってくるので、
とても焦っています。
そして、今回の見城社長は前作を超える
のではないかと感じるほど面白いです。
今回収録される中でも私の好きな言葉、
「絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ」
以前、見城社長の著書にサインをもらった
言葉です。
この言葉を今現在サイバーエージェント 社内に多数いる新規サービスを創っている 人たちに捧げたいと思います。
絶望しきって死ぬのは幸せなことだと思う。
圧倒的に努力し、集中し、持てる力の全て
出し切って、それでも尚ダメだったとするならそれは望み絶たれる絶望です。
それなら悔いを残さず、清々しい気持ちで
自分に対しても誇れると思います。
しかし、やり残したことがあったり、
全力を出し切れなかったり、中途半端に
気が散っていたとしたら、悔いを残すと
同時に、望みも残して諦めもつかず、
死んでも死にきれません。
私も起業した頃は起きている時間は全て
仕事に費やし、友人も彼女も睡眠も食事も
全てを犠牲にして成功に賭けていました。
よく取材を受けて、
「若いのに不安とかはないですか?」
と聞かれるたびに
「これでダメだったとしたら仕方ないと
思えるくらいやってるんで」 と答えていました。
起業した頃は、成功を強く信じて頑張った
と思われがちですが、実際は違います。
失敗しないために、思いつく限りの全て
の努力をやり尽くしていたのです。
現実は成功より失敗する確率のほうが
遥かに高いのを知っていたからです。
それと同じく新サービスを創る際にも
成功より失敗する確率のほうが高いです。
にも関わらず、多くの人は一握りの成功例
を参考にサービスを考え、自分も成功する
と信じ込みます。
それよりも、遥かに多い失敗例のほうにも
目をむけ、厳しい現実を知る必要があります。
そして悔いを残すパターンの多くは致命的な問題の見落としです。
自分たちのサービスをひたすらネガティブ チェックして、その現実から目をそらさず、できる限りの全ての手を尽くしてその日を待つことが大事なのです。
映画の興行成績は初日の入りで大体判る
と聞きますが、ネットサービスもローンチ後1週間も経たずに9割がたは可能性が
あるのかダメなのか判明します。
その時に絶望しきって諦めるしか無かった
としても、持てる力を全て出し尽くして
いればそこから何かを学べるはず。
その日のために、今を熱狂して仕事しましょう。田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot うちの社員はポジティブでいいやつが
多いと思います。
それは会社の良さであり、ずっと大事に
したいところではありますが、
先日、まさにポジティブでいいやつで、
社内で誰からも好かれるタイプの
事業責任者をミーティングで頭ごなしに
叱りました。
「戦略の詰めが甘いんだよ!」
彼を始め、その部署のメンバーは
疑いようもなく一生懸命頑張りますが、
トップの戦略が甘ければ、自分含めて
みんなの努力が全て水の泡です。
そのため、戦略を描くトップの立場の
人の責任は重大です。
これでもかというくらい抜け漏れを
チェックして、あらゆる可能性を吟味し、
しらみつぶしに問題を洗い出し、
後悔のないよう、最後までしつこく、
しぶとく考え抜かなければなりません。
ところが、ポジティブな性格の人は、
良い戦略アイデアがひとつ見つかると、
「いける!いける!」
「あとはやるしかない!」
とか言って、すぐみんなで飲みに行って しまったりします。
トップが戦略の拙さを、前向きさや熱さで
誤魔化してはいけません。
ここで最後までネガティブに戦略をチェックしなかったわずかな時間が原因で、
これから始まる戦略を実行するための
長い日々が、徒労に終わってしまうかも
知れないのです。
また、戦略を考える際には、
時には競争相手に打ち勝たなければ
ならないので、競合が嫌がることや、
相手を出し抜くような発想も必要に なってきます。
そんなとき、性格のいいやつで、
人が嫌がることをするのが苦手な人も
います。
また、いい人が大多数のチームでは
意地の悪い作戦が言い出しづらい 雰囲気になったりもします。
それでは戦いの前に戦略を放棄している
ようなものです。
私は新卒の頃、
「徹底的に敵をへこます法」という本を
読むように勧められて、この本に影響を
受けましたが、我ながら悪いやつでは
ないと思いますが、仕事上は決して
お人よしでもないと思います。
ポジティブでいいやつの落とし穴とは、
戦略が甘くなりがちということですが、
思い当たる人は注意が必要だと思います。
今日は夕方から、3時間半かけて、
とある事業ドメインの重要な戦略会議を
行いました。
厳しい市場環境と向き合って、
自社の戦略をネガティブに見直し、
競争相手ができないこと、
同業者の一歩先を読んだ動きなど、
時間の許す限り考え抜きました。
この時間は結構「ネガティブで悪いやつ」
だったと思います。田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot 先日、ベストセラー「伝え方が9割 」の著者、佐々木圭一さんと対談させて頂きました。
その時に佐々木さんから印象的な話を
お聞きました。
それは、日本のメーカーなどの企業は
どうして製品の魅力の伝え方が下手なのか、という話題から出た話なのですが、
「国民の大半が移民によって成り立つ
アメリカのような多民族国家では、
家庭で英語を話してない人にも 伝わるように努力している」
というような話でした。
逆にいえば、日本人は阿吽の呼吸の ような感覚で伝わると思っているので、
そこの意識が足りないということです。
この話を、ここ数日間の会議で何回も
引用させてもらいながら、Amebaの
プロデューサーにUIの分かり難さを
指摘しました。
「色々盛り込み過ぎてるから、何のページ
を意味していいるのか分からない」
「この内容では、前後の文脈が違う。
それではユーザーが混乱する」
「意訳し過ぎてて、もう意味不明」
「なんでもチュートリアルで説明するな。
皆が読んでくれるわけではない」
などなど。
我々日本人は、同一言語を話す社会
で暮らしているため、
他人に何かを伝えることは、本来 とても難しいということを忘れる傾向が
あるのではないでしょうか。
「相手がなに人であっても分かる ように作ってくれ」
最近そればっかり言っていますが、
強く意識するくらいがちょうど良いと
思います。田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot 昨年4月に経営者ブログを始めてから丸1年が経ちました。お付き合いくださり、ありがとうございます。
初回の記事のタイトルは「新人へ贈る、気を付けるべき『付き合い』方」。サイバーエージェントの入社式で新人に贈った言葉を紹介しましたが、今年も、入社式で話すことをこのブログにも記したいと思います。
今年の入社式では、「勝負どころの見極め方」についての話をしようと思っています。
最初から最後まで全力疾走をして勝つマラソン選手はいません。社会人も長距離走です。常に張り詰めて仕事をし続けられる人はいません。自分なりのペース配分を考え、ここぞというところを見極めて集中し、死に物狂いで頑張る。それができれば、しばらくは「楽」になれます。
勝負どころの重要性は、新人の皆さんも受験や就職活動で味わってきたことでしょう。例えば、中学や高校時代のほとんどを遊んで過ごしてきたとしても、大学受験時のほんの短期間に集中して努力し、有名大学に入ることができれば、その後の人生でメリットを享受できる。良いか悪いかはともかくとして、人生では勝負どころで頑張れるかどうかがその後を大きく左右することが多いのです。
ただし、頑張る前に必要なのは「その時」を見極めることです。社会人になると勝負どころの見極めは難しくなります。期末試験やインターハイ、受験や就職活動など、学生時代であれば多くの勝負どころが、周囲と同じタイミングで訪れてきました。ですが社会に出れば、勝負どころは人それぞれ違うタイミングで訪れます。横並びで訪れるのはまれであり、8~9割はじっと耐えて待つ時間になります。耐えることができず、闇雲に勝負に出る人は、ほとんどが負けてしまう。要するに、功を焦って自滅するのです。
ほんの少しの勝負すべき時間と、耐える長い時間の繰り返しの中で、いかに時機を見極め、正しい時に勝負強さを発揮できるか。つまり、社会人にはこれまで以上に、自分に勝負どころが訪れていると認識する能力が求められるのです。では、どう見極めればいいのか。
ポイントは「環境の変化があり、かつ自分に関係があることかどうか」です。
自力では何ともならない環境の変化によって、誰にでも「明らかにここが勝負どころだろう」というタイミングが年1回や2回くらいは訪れます。例えば、政府や会社の方針が変わったり、市場にブームが到来したりしたことで、関連する自分のプロジェクトや立場にスポットライトが当たった、といった時。社長が「これからはクリエイティブが重要だ」と言い出したら、その時こそ、クリエイター職の社員にとっての勝負どころなのです。
私自身、そうした勝負どころで集中して頑張り、飛躍をつかみましたが、それ以外の期間はおとなしくしていました。サイバーエージェントで言えば、起業した頃とその後の「ネットバブル」の頃は勝負どころでした。最近では、世の中がスマートフォンへとシフトした変化を勝負どころと捉え、社内の体制も一気に変えました。チャンスはわりと見えやすい形でやってくるのですが、意外とそこに気づいていない人は多いのではないでしょうか。
勝負どころの見極めには、「平常心」も求められます。マイペースで判断することが大事であり、周囲に惑わされてはいけません。例えば、同期が成果を出したから、自分もここで勝負をかけよう、というのは、早く功績を上げたいという焦りであり、先に述べたように自滅につながります。焦りは「欲」からくるもの。欲が絡むと、人は間違ったり、判断を見誤ったりするものです。
ですから、これから社会人になる新人には、ぜひ、平常心で環境の変化を見つめ、それぞれの勝負どころで力を発揮していただきたいと思います。ただし「例外」があります。入社1年目は、2年目、3年目より目立つことができる「ボーナス期間」。誰もが共通して迎える、社会人最初で最後の横並びの勝負どころと言えます。研修期間だとしても、そこで頑張って注目を浴びれば、その後の社会人生活に大きな好影響を与えることができます。
新入社員諸君、1年目のスタートダッシュは全員が勝負どころだよ。これを、今年の新人に贈る言葉としたいと思います。田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot 昨日のブログがなかなか好評だった
(そんな気がする)ので、付け足しです。
自信がある人もまた、戦略が甘く なりがちです。
自分の力を100だと見積もって
いた場合、100の力なら勝てる
戦略を立案します。
しかし、それでは実際の力が80だったり50だったりしたら勝てません。
自信がなくて、
自分の力は本当は10くらいだと
かなり厳しく見積もっていたならば、
それでもなんとか勝てる戦略を
必死にひねり出し、それで実際の力が
30とか50であれば、余裕で勝てます。
会社の戦略は、実際の力が10で
あっても勝ち残れるように考えるべき
だと思います。
3年前のサッカーW杯のとき、
岡田ジャパンが本場直前の強化試合で
連敗を喫して、相当厳しい大会になると
予想され始めてから、突然強くなった
ということがありました。
恐らく、弱者でも勝てる戦略に切り替え、
チームの意識も変わったのだと思います。
別の話で、会社で最年少の人を抜擢したり
すると、成功する確率は実は高いです。
自分くらいの経験しかない者には
難しいと見積もって頑張るからです。
そのあと、その人が成功した後に
抜擢した人は、今度は同世代ができた
のだからいけるんじゃないかと
甘い見積もりで失敗しやすくなります。
もちろん、最後は自分を信じることも、
プライドや自尊心も大事です。
でも、戦略を考えるときは、自分たちの
実力を相当低く見積もるくらいで ちょうど良いのだと思います。田中悠太 藤田晋bot藤田晋bot 今日の役員会であした会議の振り返りを
しているときに、プレゼンを聞く立場の私が会議中に、
「結論ファーストで頼むよ」
「話が長いよ」
と何度も言った件について、その理由は何か?という話になりました。
自分の中ですぐうまく説明できなかった
のですが、いつも同じように感じています。
実際、長々と説明されるアイデアは
ろくなものがなくて、それを喋りで誤魔化そうとしているような気もします。
それに自分が既に知っていることを延々と
説明されると、(何も相手の立場を知らずに提案してるな)とか(今頃こんなことを勉強したのか)とか頼りない印象を与え、聞く耳を持つ気が萎えてしまうというのもあると思います。
大抵の場合、重大な決断をする相手の
ほうが自分よりもそれについて真剣なので、もっと詳しいのです。
相手にとって重大な決断を迫るような
提案をする場合、
1.要点を伝える。 2.疑問に答える。
それだけで十分だと思います。
アイデアの要点を簡潔に伝えて、 相手が(良いな)と感じれば、
それが大事な話であればあるほど、
ネックになるポイントが次々と思い浮かびます。 準備をしていてそれらの疑問に応えられれば、(なるほど)ということになりやすいです。
以前、社内でクライアントに提出した
プレゼン資料を集めたときに、
「これは決まらなかったんですが・・」
というのは分厚くて立派な資料で、
「大型受注した資料です」
とぃうのは要点だけを記載した資料だった
ことがあります。
今回の話は社内のことですが、
通常業務でも同じようなことが結構起きて
いるのではないでしょうか。